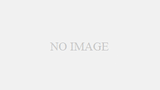927年に編纂された延喜式神名帳に「阿波国 名方郡 御間津比古神社(みまつひこのかみのやしろ)」と記された神社があります。名東郡佐那河内村にある御間都比古神社が延喜式神名帳に記された神社だとされています。
御間都比古神社を行く!
御間都比古神社は、四国山地から東の紀伊水道へ向かって流れ込む園瀬川の上流域、名東郡佐那河内村下に鎮座しています。

広い境内は、樹木や草が生い茂り、物静かな様子は、異世界に迷い込んだような気分になります。鳥居をくぐり、社殿まで行くと、「御間都比古神社」と書かれた石柱が立っています。

神社沿革「徳島県神社誌」「佐那河内村史」より
- 創始年代不明 第13代成務天皇のときに、観松彦色止命の9世孫の韓背宿禰が長国造となり、祖神の観松彦色止命を長峯の中腹に奉祀した。
- 927年 延喜式神名帳に列せられる。
- 戦国時代 社殿破壊され、その後は跡地にて祭祀を行う。
- 天保11年(1840年) 社殿改築。
- 明治21年(1888年) 一坪ほどの社殿が建てられるが、神社明細帳に脱漏したため社殿は荒廃する。
- 大正9年(1920年) 宮内省諸陵考証官の実地調査がされる。
- 大正14年(1925年) 境内を拡張し、本殿を改築する。
- 昭和9年(1934年) 寄付金により社殿改築、翌年落成式を行う。
徳島県神社誌では、御間都比古神社の祭神は、御間都比古色止命(みまつひこいろとのみこと)となっています。
しかし、延喜式神名帳に記された御間津比古神(みまつひこのかみ)の正体については諸説あります。
「御間津比古神=観松彦香殖稲命」説
初代神武天皇以降、欠史八代とされる実在が疑われている天皇の中に「みまつひこ」という名のついた天皇がいます。
第5代孝昭天皇の名は、古事記では 御眞津日子訶恵志泥命(みまつひこかえしねのみこと)、日本書紀では 観松彦香殖稲命(みまつひこかえしねのみこと)と記されています。
つまり、御間津比古神は、第5代孝昭天皇だというのです。

うーん 延喜式内社で天皇を祀っている神社なんてあまり聞いたことがないなあ。しかも、小社だし・・・。
1800年頃に徳島藩士であった赤堀良亮氏が編纂した「阿府志」では、御間都比古神社の祭神は、第5代孝昭天皇である観松彦香稲命であるとしています。
また、長谷川貞彦氏による「阿波式内神社考」でも「観松彦香稲天皇とは孝昭天皇を申し奉る」と、御間都比古神は、第5代孝昭天皇であるとしています。
阿波古代史研究家のバイブルともいえる岩利大閑氏の「道は阿波より始まる」でも、御間都比古神社は第5代孝昭天皇をお祀りしているとして阿波古代史を論じています。

私もそうであったら面白いと思っていろいろ調べたものの、その根拠といえる状況証拠がみつからない・・・。
「御間津比古神=観松彦色止命」説
徳島県神社誌が記す 御間都比古色止命(みまつひこいろとのみこと)とはどのような人物なのでしょうか。
阿波国には、かつて粟国と長国の2国があり、それぞれ国造がヤマト王権によって任命されていたことが先代旧事本紀国造本紀に記されています。
「粟国 軽嶋豊明朝御世。高皇産霊尊九世孫千波足尼定賜国造」
「長国 志賀高穴穂宮御世。観松彦色止命九世孫韓背足尼定賜国造」
御間都比古色止命は、長国造に任命された 韓背足尼(からせのすくね) の祖先にあたる人物です。
長国とは、徳島県を流れる吉野川の南方とされ、その範囲は、現在の海部・那賀・勝浦・阿南・小松島・佐那河内・徳島市南部の一部と考えられています。
御間都比古神社の神社由緒
長国の祖神 観松彦色止命、はじめて佐那県に移住し、山野を開き水田を起こし、海浜の地に漁業を教えて産業を開発せられた。成務天皇のときに、観松彦色止命九世の孫、韓背足尼が長の国造となり祖神観松彦色止命を長峰の中腹に奉祀し・・・
「徳島県神社誌」
神社由緒は、長国の祖神を観松彦色止命としていますが、徳島県阿南市にある延喜式内社 八桙神社(やちほこ)は、長国の祖神として 大己貴命(おおなむちのみこと) が祀られています。
つまり、観松彦色止命と大国主命は同系譜ということになります。

その根拠は?
長国造となった韓背宿禰の子孫の痕跡は、「続日本紀」に宝亀4年(773年)、阿波国勝浦郡領の長費人立が「長費」という姓を「長直」に戻してほしいと国司に訴えた件が記されています。
815年の「新撰姓氏録」には、この阿波国の長氏と同族と思われる氏族がいくつか記されています。
- 和泉国 神別 長公 大奈牟智神児積羽八重事代主命之後也
- 摂津国 神別 我孫 大己貴命孫天八現津彦命之後也
- 大和国 神別 長柄首 天乃八重事代主神後也
さらに、「続日本紀」に「摂津国 長我孫葛城とその同族三人に長宗宿禰の姓を賜う 事代主命八世孫忌毛宿禰の苗裔也」という記述があり、長国に居住していた豪族である長氏も大己貴命や事代主神の末裔であることが推測できます。
長国造となった韓背宿禰の子孫が長氏であるとすれば、長氏は阿波の長国から始まった氏族であり、長姓を名乗る「和泉国長公」や「摂津国長我孫」「大和国長柄首」らもその旧地は阿波ということになります。

ここにも事代主神が阿波神である証拠があった・・・。
ということで、「古代豪族系図集覧」(近藤敏喬 編)には、
大国主命ー事代主命ー天八現津彦命ー観松彦色止命・・・・・・韓背宿禰
という系譜が記されています。
これらのことを根拠として、多くが「御間津比古神=観松彦色止命」としています。
徳島藩が編纂し、1815年に完成した「阿波志」では、「三木松即観松彦色止命を遠孫の韓背宿禰が祀ったもの」と記しています。

地元では「三木松神」として祀られていたものが、「阿波志」の記述をうけて、1840年に社殿が改築され、「御間都比古神社」となったのではないだろうか?
大麻神社神職の永井精古氏は、1800年頃に著した「阿波国式社略考」のなかで、「阿府志」の記述について「孝昭天皇は観松彦香殖稲命とは申し奉るも色止命という御別名は古書に見えざれば別人と知られたり、されば国造本紀にあわせるしかない。」と「御間都比古神=観松彦香殖稲命」を否定しています。
その他の説
「阿波志」「阿府志」の記述をみると、現在の御間都比古神社は、地元では「三木松神」とよんでいたようなのです。
実際、1743年の「寛保御改神社帳」の佐那河内村の項にそれらしき神社は記載されていません。
「阿府志」も「長峯(中峯とも)にあるから長国造」で、「三木松神と呼んでいるのが観松ノ神である」と根拠が少々苦しいのです。
前述の大麻神社神職の永井精古氏も「長の一字だけでそういっているけど、長国は那賀郡では?」と、延喜式神名帳に御間津比古神社が名方郡の項に記されていることを根拠に疑問を呈しています。

つまり、ここが御間津比古神社ではないということ・・・?
「式内社の研究」のなかで、志賀剛氏は御間津比古神社を所在不明として、播磨国風土記に「弥麻都比古命が井を治めた」という記述があることから、御間津比古神は井すなわち水に関する神様の水間津比古神だったのではないかとして、石井町にある中島新宮本宮神社が延喜式神名帳に記された御間津比古神社ではないかと推察しています。
御間津比古神という神名について
実は、古事記には「御間津」の名が付く人物が他にも登場します。しかも2人も・・・。
第9代開化天皇と伊迦賀色許賣命(いかがしこめのみこと)との間に、御眞木入日子印恵命(みまきいりひこいにえのみこと)と御眞津比賣命(みまつひめのみこと)が生まれています。
御眞木入日子印恵命は第10代崇神天皇となります。この崇神天皇の妃の名も御眞津比賣命といいます。この、御眞津比賣命は第9代開化天皇の兄の大毘古命(おおひこのみこと)の娘です。
古代のことですから、兄妹婚が無いとは言い切れませんが、崇神天皇の妃について古事記は、はっきりと大毘古命(おおひこのみこと)の娘と記していますから、おそらく2人の御眞津比賣命は別人であると考えられます。
御間津比古や御眞津比賣命の「ミマツ」は、おそらく地名に由来していると思われます。
例えば、第3代安寧天皇の名は、師木津日子玉手見命(しきつひこたまてみのみこと)といいます。さらに、第3代安寧天皇の第3子には、師木津日子命という名が付けられています。これは、安寧天皇の母や妃が師木縣主の祖とされていることから、母方の地名「シキツ」から付けられたものと思われます。
「シキ」とは河川敷の「シキ」で、「ツ(津)」も水辺や水運に関係のある言葉です。
「ミマツ」も同じように考えると、「ミマーツ」で、水辺や水運に関係する名前だと思います。
第5代孝昭天皇である御眞津日子訶恵志泥命(みまつひこかえしねのみこと)の母も古事記では、賦登麻和訶比賣命(ふとまわかひめ)またの名を飯日比賣命(いいひめ)といい師木縣主の祖と記されています。つまり、「シキツ」の「ツ」と同じというわけです。
長国造の韓背宿禰の祖の観松彦色止命(みまつひこいろとのみこと)も事代主神や大己貴命を祖先としています。事代主神や大己貴命は、そもそもは、海人族が祀っていた神様です。観松彦色止命の「ミマツ」も「ミーマツ」ではなく「ミマーツ」で、海人族を示しているのかもしれません。
播磨国風土記に登場する弥麻都比古命(みまつひこのみこと)も「井を治めた」という記述があることから、おそらく水辺に関係する地名もしくは海人族であったかもしれません。
観松彦色止命でつながる阿波と隠岐
国造本紀には、阿波の長国の他に、観松彦色止命を祖とする国造がいます。
意岐国造 軽島豊明朝(応神) 観松彦色止命5世孫 十揆彦命
意岐国造とは現在の島根県隠岐島のことです。隠岐島ですから海人族が本拠地としていても不思議ではありません。このことからも観松彦色止命の「ミマツ」はやはり海人族に付けられた名前だと言えます。
隠岐国造の子孫がである意岐氏が社人を務める延喜式内社に玉若酢神社という神社があります。主祭神が玉若酢神命でを主祭神とし、大己貴命・須佐之男命・稲田姫命・事代主命・須世理姫命を配祀しています。

THE 海人族って感じ・・・。
この玉若酢神社は、総社ではありますが一の宮ではありません。隠岐国一の宮は同じく延喜式内社の名神大社である水若酢神社となっています。この水若酢神社の社人は忌部氏が務めています。(西郷町史下巻「触頭の設置」より)

おおっー忌部氏・・・。
さらに、鎌倉時代になりますが、平家討伐の功績により隠岐守護地頭を拝領したのが佐々木定綱という人物です。佐々木定綱は、佐々木四兄弟として有名で、源平の戦いで活躍し、鎌倉幕府の成立に大きな役割を果たしています。そして弟の佐々木経高は、阿波守護として阿波国を拝領しています。
隠岐と阿波には不思議な関係があるようです。
まとめ
名東郡佐那河内村にある御間都比古神社は、「長峯にある三木松神を祀る」ということから「長国の祖の観松彦を祀る」とされ、「観松彦」から「第5代考昭天皇」であるという説にまでなったようです。
いろいろ調べてみて、御間都比古神社の祭神は、長国造の祖である観松彦色止命が有力な説だと思います。しかし、宮内省が調査に来ていたり、その時に奈良に遷す話があったりと、第5代孝昭天皇だという説も気になります。
阿波には、ほかにも欠史八代の天皇に関わるモノがたくさん残っていますから・・・
それにしても、阿波国と隠岐国に意外なつながりがあることがわかりました。隠岐国を調べてみることで、御間津比古神社のことも何かわかるかもしれません。


-6-1-160x90.jpg)
-34-160x90.jpg)