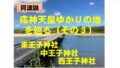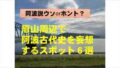大唐国寺は、徳島県板野町川端にあった寺院です。奈良時代後期から平安時代前期に創建され、江戸時代後期までその記録が残っています。千年以上も続くも、突如歴史から消え去ります。そんな大唐国寺を掘り下げてみました。
大唐国寺の現在は?
大唐国寺跡は、JR川端駅から北へ約1kmほど緩やかな坂を上った小高い丘にあります。
それ以上奥は、「富の谷」と呼ばれており「なんとか阿波説」では結構登場する場所です。
グーグルマップが示す場所へ行ってみましたが、ご覧のとおり何もありません。

この奥が「唐土(もろこし)」、さらにその奥が「唐土谷(もろこしだに)と呼ばれている地域です。
創建年代や規模は?
大唐国寺は、文化12年(1815年)に編纂された徳島藩の地誌「阿波志」に川端村の唐土(もろこし)にあったことが記載されています。山号も含めた寺院名は「唐土山大唐国寺」です。

江戸時代後期まではあったんだ
また、天文21年(1552年)に定められた「阿波国念行者修験道法度」に「河端大唐国寺」の名が見えることから当時は山伏の拠点寺院であったと考えられています。
大唐国寺の創建年代や規模はよくわかっていません。
ただ、大唐国寺があったとされる周辺の田畑からは多数の古瓦が出土しており、「阿波国仏教史(三好昭一郎著)」において、出土瓦の種類も数も多いことから、大唐国寺は建造物の数も多い相当な大寺院であっただろうと推察しています。
また、「新修国分寺の研究第5巻上(角田文衛編)」には、大唐国寺出土瓦の中に平城宮出土の瓦とよく似た文様があると記されていることから、大唐国寺の創建は、奈良時代後期から平安時代前期だと思われます。
平安時代前期の創建と考えても、江戸時代後期まで存在していたということは、約1000年間もあったことになります。
大唐国寺を建立したのは?
「大日本地名辞書」(吉田東伍著)に
板西村川端あり、塩彦祠を鎮守とす、この地蓋(おもうに)百済氏の旧居。寺背に大唐谷の字あり、又この村に古墓の石槨あり、今祀りて若宮と称す。
との記述があります。
唐土という地名もそうですが、吉田東吾は、「塩彦祠を鎮守とす」から百済氏の領地であると推測しています。

塩彦って誰?
「新撰姓氏録」をみると、「塩君」という人物をいくつかの氏族が先祖としています。「塩彦」はこの「塩君」だと考えられています。
「葛井宿禰 菅野朝臣同祖 塩君男味散君之後也」
「宮原宿禰 菅野朝臣同祖 塩君男智仁君之後也」
「津宿禰 菅野朝臣同祖 塩君男麻侶君之後也」
「中科宿禰 菅野朝臣同祖 塩君孫宇志之後也」
そして、四氏族が同祖とする菅野朝臣を「新撰姓氏録」でみると、
「右京 諸蛮 百済 菅野朝臣 出自百済国都慕王十世孫貴主王也」
とあります。これらのことから、「塩君」は、百済の王族の末裔だということになります。
「新撰姓氏録」掲載の諸蛮(渡来系氏族)で、「八色の姓」の最高位である「朝臣」を賜っているのは、「和(やまと)朝臣」「百済朝臣」「菅野朝臣」の三氏だけです。
「和朝臣」の和氏は、桓武天皇の母の出身氏族、「百済朝臣」の百済王氏は、660年に滅亡した百済最後の王の義慈王の子の善光が百済王氏を賜ったことに始まります。
「菅野朝臣」を賜った津連真道の津氏は、和氏や百済王氏と比べれば、それほど高級貴族でもなく、異例の大出世と言われています。
津連真道は、かなり仕事のできた人物てあったようで、延暦9年(790年)に朝臣への改正のための上表文を提出しています。
真道らの本系は百済国の貴須王から出ました。貴須王は百済が建国して第十六代の王であります。〈略〉応神天皇が上毛野氏の遠祖である荒田別を百済へ遣わし、有識者を招へいされました。貴須王はつつしんでその趣旨を聞き入れ、一族の中から選抜して、その孫である辰孫王をつかわし、日本の使臣に従って入朝させました。仁徳天皇は、辰孫王の子である大阿郎王を近くにはべらせました。大阿郎王の子は亥陽君であり、亥陽君の子は午定君であります。午定君は、三男を産みました。長子は味沙であり、仲子は辰爾であり、季子は麻呂であります。これからはじめて別れて三姓となり、おのおのの職務によって氏を名のりました。葛井・船・津の連がそれであります。「日本史に生きた渡来人たち(段煕麟著)」より引用
「新撰姓氏録」の葛井宿禰の味散君が味沙、津宿禰の麻侶君が麻呂とすると、宮原宿禰の智仁君が辰爾ということになります。
つまり、それらの父が塩君なのですから、塩君は午定君ということになります。

川端村の鎮守として「塩彦祠」に祀られたのは百済王族の子孫の午定君
「新撰姓氏録」みると、菅野朝臣の同祖とする氏族に「船連」がいます。
「船連 菅野朝臣同祖 大阿郎王三世孫智仁君之後也」
船連については、「日本書紀」に、欽明天皇14年(553年)に、勅命を受けた蘇我大臣稲目宿禰が、王辰爾(おうしんに)いう人物に船の税を記録させ、この功により船氏の姓を賜り船史(ふねのふひと)となったことが記されています。
この王辰爾の弟の宇志が、津史(つのふひと)を賜ったことが、日本書紀敏達天皇3年(574年)に記されています。「史(ふひと)」とは物事を記録する職の事です。
「新撰姓氏録」の「中科宿禰 菅野朝臣同祖 塩君孫宇志之後也」の「宇志」が王辰爾の弟で津氏の祖になります。
津氏はおそらく、賜ったその名や「史」という職から、港の管理・記録を任された氏族であると思われます。
川端村に、「塩彦祠」を祀り、その後、大唐国寺を建てたのは、百済系渡来人の津氏ではないかと思うのです。
川端から約3kmほど南西に行ったところに「郡頭(こおず)」と呼ばれる古代の海上交通の要所がありました。郡頭から大坂を経て引田へ抜ける道は、古代から「阿波-讃岐」の幹線道路でした。郡頭の港には、多くの物資や人が集まってきたに違いありません。
その港の管理・記録を朝廷から任されたのが津氏ではなかったかと思うのです。
津氏の祖「宇志」
津氏の祖で王辰爾の弟の宇志ですが、板野町川端の大唐国寺跡から東へ約5kmほど行ったところに、延喜式内社の「宇志比古神社」があります。



もしかしてその宇志?
「延喜式」によると、南海道の駅に「石隅」という港が記されており、宇志比古神社の南東約500mのJR大谷駅の南側の「石園(いその)」に比定されています。石園港は、昭和に入ってからも大谷瓦の京阪神への積出港として大型船が出入りしていたそうです。

郡頭の港を管理していた津氏が「塩君」を「塩彦祠」に祀り、石隅の港を管理していた津氏が「宇志君」を「宇志比古祠」に祀ったということか
実は、延喜式内社の「宇志比古神社」がどこにあったのかわかっていません。
現在の宇志比古神社も明治になってから「八幡宮」から改称したもので、確定ではありません。
よって、祭神の宇志比古命が一体誰なのかについても諸説あります。
このブログでも以前に「宇志比古神社」を紹介しましたが、「郡頭」「石隅」の港の存在や津氏の職業、川端の「塩彦祠」の存在などから、「宇志比古」は百済系渡来人の王辰爾の弟の宇志の可能性が高いと考えます。
状況証拠はそろっているのですが、阿波には津氏の痕跡はまったくありません。
田上郷戸籍にみえる百済系氏族
阿波古代氏族を語る上で貴重な資料に「延喜2年(902年)板野郡田上郷戸籍断簡」という資料があります。そもそも板野郡田上郷がどこにあったのか不明なのですが、「徳島県史」は、板野付近であろうと推測しているのでこれにならい妄想してみます。
その田上郷戸籍に「飛鳥部」と「錦部」という氏族が掲載されています。弘仁6年(815年)に編纂された「新撰姓氏録」によると、「飛鳥部」は「飛鳥戸造」、「錦部」は「錦部連」として記載があり、どちらも百済系の氏族です。

つまり平安時代に百済系の人々が住んでいたということ
ただ、田上郷戸籍には、物部子益という41歳の男性が「宇志祝部」をしていたと記されています。祝部とは神に奉祀する者のことであり、宇志比古神の祝部と解釈すると、宇志比古神を祀っていたのは物部氏ということになります。

宇志比古は王辰爾の弟の宇志じゃないのか?
まとめ
妄想をまとめてみると、
大唐国寺は、平安時代初期の800年頃に、港の管理・記録のために朝廷より派遣された百済系の津氏によって建立されたと考えます。当時津氏は、津連真道が中央官僚として「朝臣」を賜るなどかなりの勢いがありました。大唐国寺はそんな津氏の勢いを地方でも象徴するものであったかもしれません。
927年に編纂された延喜式神名帳に記された「宇志比古神社」が津氏一族に関わるものであるとすれば、宇志比古神社への朝廷からの幣帛も、この頃、中央官僚として影響力のあった津氏の後裔の菅野朝臣氏の意向があったのかもしれません。
その後、宇志比古神社の所在さえわからなくなってしまったということは、何らかの理由で、奉斎する津氏の後裔一族が阿波から姿を消したと思われます。
大唐国寺も、「阿波志」に「天文中優婆塞居る」と書かれています。「優婆塞」とは在家の仏教信者のことで、僧侶ではありません。天文21年(1552年)に定められた「阿波国念行者修験道法度」に「河端大唐国寺」と記されたころには、すでに、寺院と言えるほどの規模はなかったと思われます。
つまり、大唐国寺も宇志比古神社が衰退していったのと同じように、衰退していったと考えられ、かろうじて行者の拠点としてその名が残されたものと考えられます。
このように妄想してみましたが、津氏の一族の痕跡が阿波にない以上、なんとも心細い説となります。
関連記事