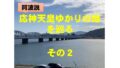饒速日命(ニギハヤヒノミコト)
天火明命
妃 天道日女命
※「海部氏勘注系図」では大己貴神の娘
【1世孫】
天香語山命(アマノカゴヤマノミコト)
※饒速日命に追従し天降り,紀伊国熊野邑に居る。亦名 手栗彦命 高倉下
妃:穂屋姫(ホヤヒメ)
※異腹妹とあるので饒速日命の娘
※「海部氏勘注系図」では,火明命と佐手依姫命(亦名市杵嶋姫命)の娘
【2世孫】
天村雲命 亦名 天五多手命(アマノイタテ)
妃:阿俾良依姫(アイラヨリヒメ)
①天忍人命 ②天忍男命 ③忍日女命
妃:伊加里姫命(イカリヒメ)
①倭宿禰命(亦名:天御蔭命) ②角屋姫命(亦名:葛木出石姫)
※「海部氏勘注系図」では,天村雲命が丹波国に天降って,伊加里姫命を娶る。
※京都府舞鶴市京田に伊加里姫神社がある。
【3世孫】天村雲命-阿俾良依姫
天忍人命(アマノオシヒト)
妃:角屋姫命(ツヌヤヒメ)亦名:葛木出石姫
①天戸目命 ②天忍男命
☆角屋姫命の亦名が葛木出石姫であることからして,但馬出石と大和葛城に何らかの関係があると考えられる。
天忍男命(アマノオシオ)
妃:賀奈良知姫(ガナラチヒメ) 葛木国造の剣根命(ツルギネノミコト)の娘
①瀛津世襲命 ②建額赤命 ③世襲足姫命
忍日女命(オシヒメ)
【3世孫】天村雲命-伊加里姫命 ▼海部氏勘注系図のみ
倭宿禰命
※「海部氏勘注系図」では,神武天皇に息津鏡・辺津鏡を以て奉仕し,大和国で白雲別神の娘の豊水富命を娶って,笠水彦命を産んでいる。
※亦名を天御蔭命といい,京都府舞鶴市に彌伽宜(みかげ)神社の祭神として祀られている。神社由緒では,天御蔭命の亦名は天日一箇命であるとしている。
※先代旧事本紀には,伊加里姫命と倭宿禰命は登場しない。
【4世孫】天忍男命-賀奈良知姫
瀛津世襲命(オキツヨソ)
※葛木彦命 ※尾張連の祖 ※第5代孝昭天皇紀に大連を務める。
☆瀛津世襲命の祖父は,葛城国造の剣根命
建額赤命(タケヌカアカ)
妃:葛城尾治置姫
世襲足姫命(ヨソタラシヒメ)亦名 日置日女命 ※孝昭天皇后 孝安
※「古事記」では,奥津余曽(オキツヨソ)の妹の余曽多本毘売命(ヨソタホビメノミコト)が第5代孝昭天皇(ミマツヒコカエシネノミコト) の皇后となり,第6代孝安天皇(オホヤマトタラシヒコクニオシヒトノミコト)を産んだとある。
【4世孫】天忍人命-角屋姫命
天戸目命(アマノトメ)
妃 葛木避姫(サクヒメ)
①建斗米命 ②妙斗米命
天忍男命
※大蝮壬生連の祖
【4世孫】倭宿禰命-豊水富命 ▼海部氏勘注系図のみ
笠水彦命
※第2代綏靖天皇に天御蔭之鏡を以て奉仕する。
妃:笠水女命
①笠津彦命
【5世孫】建額赤命-葛城尾治置姫
建箇草命(タケツツクサ) ※多治比連 津守連 若倭部連 葛木厨直の祖
【5世孫】天戸目命-葛木避姫
建斗米命(タケトメ)
妃 中名草姫 ※紀伊国造 智名曽の娘
妙斗米命(タエトメ) ※六人部連の祖
【5世孫】笠水彦命-笠水女命 ▼海部氏勘注系図のみ
笠津彦命
妃:笠津姫命
①建田勢命
【6世孫】建斗米命-中名草姫
建田背命(タケタセ) ※神服連 海部直 丹波国造 但馬国造の祖
※「海部氏勘注系図」では,「一云建登米之子」ともされているので,これなら,先代旧事本紀と一致する。建田勢命は,初めは,丹波国丹波郷を治めていたが,山背国久世郡水主村に移ったので,山背直等の祖とされている。その後,大和国に移り住み,葛木高田姫命を娶り,建諸隅命を産んだ。
建宇那比命(タテウナヒ)
妃 節名草姫 ※城嶋連の祖
建多乎利命(タケタリオ) ※笛吹連 若犬甘連 の祖
建弥阿久良命(タケミアグラ) ※高屋大分国造の祖
建麻利尼命(タケマリネ) ※石作連 桑内連 山辺県主 の祖
建手和迩命(タケタワニ) ※身人部連の祖
宇那比姫命
【7世孫】建宇那比命-節名草姫 ▼海部氏勘注系図では,建田勢命-葛木高田姫命
建諸偶命(タケモロズミ)
妃:諸見己姫 ※葛木直の祖 大諸見足尼(オオモロミノスクネ)の娘
①倭得玉彦命(ヤマトエタマヒコ)
※第5代孝昭天皇紀に大臣を務める。
大海姫命(オオアマヒメ) 亦名:葛木高名姫命
※第10代崇神天皇の妃となり,八坂入彦命(ヤサカイリヒコ),渟中城入姫命(ヌナキイリヒメ),十市瓊入姫命(トオチニイリヒメ)を産んだ。
※海部氏勘注系図では,第9代開化天皇が,丹波国の丹波郡と余社郡を割いて,開化天皇妃の竹野媛の屯倉を置いたときに,建諸隅命が開化天皇に仕えたとする。
☆傍系の4世孫の瀛津世襲命が第5代孝昭天皇の大連を務めていることから,3世代も後の7世孫の建諸隅命が同時期の大臣を務めているのはおかしい。海部氏勘注系図の記述から,第9代開化天皇紀に竹野媛の屯倉設置の功績により,妹の大海姫命が第10代崇神天皇の妃となったとも考えられる。先代旧事本紀の第5代孝昭天皇の大臣というのは誤りである。
【8世孫】建諸偶命-諸見己姫
倭得玉彦命 亦名 市大稲日命(イチノオオイナヒ)
妃 淡路国谷上刀婢(タニカミトベ)
①
妃 大伊賀姫 ※伊賀臣の祖 大伊賀彦の娘
①②③④
※「海部氏勘注系図」によると,第10代崇神天皇に仕え,天照大神の遷座に関わった。
【9世孫】
弟彦命(オトヒコ)
①淡夜別命
日女命(ヒメノミコト)
玉勝山代根古命(タマカツヤマシロネ)※山代水主の雀部連,軽部連,蘇宜部首の祖
若都保命(ワカツホ)※五百木部連の祖
置部与曽命(オキベヨソ)
①大原足尼命(オオハラノスクネ)
彦与曽命(ヒコヨソ)
①大八椅命(オオヤツキ)
②大縫命(オオヌイ)
③小縫命(オヌイ)
【10世孫】
淡夜別命(アワヤワケ) ※大海部直の祖
大原足尼命(オオハラノスクネ) ※筑紫豊国国造の祖
大八椅命(オオヤツキ) ※甲斐国造の祖
大縫命(オオヌイ)
小縫命(オヌイ)
【11世孫】
乎止与命(オトヨ)
妃:真敷刀俾(マシキトベ) ※尾張大印岐(オワリノイミキ)の娘
☆国造本紀には,第13代成務天皇朝に天火明命13世孫の乎止与命を尾張国造に定めたとある。
【12世孫】4世紀初め
建稲種命(タケイナダネ)
妃:玉姫 ※迩波県君(ニワノアガタノキミ)の祖・大荒田の娘
☆建稲種命は,第12代景行天皇,第13代成務天皇に仕え,特に第12代景行天皇の皇子の日本武尊の東国遠征では副将軍として活躍した。妹の宮簀媛は,日本武尊の妃である。娘の金田屋野姫が生んだ3人の娘が第15代応神天皇の妃となり,皇后となった仲姫命は,第16代仁徳天皇を産んだ。
【13世孫】★4世紀末~5世紀初め頃
尾綱根命(オヅナネ)
※第15代応神天皇に大臣として仕える。尾張連の姓を賜り,大臣大連となった。
尾綱真若刀婢命(オヅナマワカトベ)
※第12代景行天皇の皇子の五百城入彦命に嫁ぎ,品陀真若王(ホムダマワカノキミ)を産んだ。
金田屋野姫命(カナダヤヌヒメ)
※品陀真若王に嫁ぎ,高城入姫命(たかきいりひめのみこと),仲姫命(なかひめのみこと),弟姫命(おとひめのみこと)を産んだ。 3人とも第15代応神天皇の妃となった。高城入姫命は,額田部大中彦皇子(ぬかたべのおおなかひこのみこ),大山守皇子(おおやまもりのみこ),去来真稚皇子(いざまわかのみこ)産んだ。仲姫命は,皇后となり,荒田皇女(あらたのひめみこ),仁徳天皇(大雀天皇:おおさざきのすめらみこと),根鳥皇子(ねとりのみこ)を産んだ。弟姫命は皇妃となり,阿倍皇女(あべのひめみこ),淡路三原皇女(あわぢのみはらのひめみこ),菟野皇女(うののひめみこ),大原皇女(おおはらのひめみこ),滋原皇女(しげはらのひめみこ)を産んだ。
【14世孫】
尾治弟彦連
尾治名根連
尾治意乎巳連(おわりおおみのむらじ)
※第16代仁徳天皇紀に大臣となる。
【15世孫】
尾治金連
尾治岐閉連
尾治知々古連
※第17代履中天皇に仕える。
【16世孫】
尾治坂合連
尾治古利連
尾治阿古連
尾治中天連
尾治多々村連
尾治弟鹿連
尾治多与志連
【17世孫】
尾治佐迷連
尾治兄日女連
【18世孫】
尾治乙訓与止連
尾治粟原連
尾治間古連
尾治牧夫連
※紀伊尾張連らの祖
尾張氏まとめ
尾張氏は,天照大神の孫の天火明命が高天原から丹波に降り,その子孫が丹波を本拠地としてヤマト王権創成期の主要豪族である葛城氏と婚姻関係を結ぶことで大和地方に進出し,ヤマト王権の東国支配に伴って尾張国造となり,第15代応神天皇から尾張連姓を賜ったことによる。
天日明命7世孫の建諸隅命は大和葛城の生まれで,建諸隅命は第9代開化天皇に仕え,開化妃の竹野媛の屯倉に本拠地丹波の一部を割譲するなどの功績により,妹の大海姫命は第10代崇神天皇の妃となっている。3世紀中頃には,大和葛城に住み,ヤマト王権で活躍していたことになる。
その後,4世紀初めには,ヤマト王権の東国進出にともなって,11世孫の乎止与命が尾張国造となる。その子の建稲種命は,第12代景行天皇の皇子である日本武尊の東国遠征の副将軍として活躍し,妹の宮簀媛は日本武尊の妃となる。建稲種命の3人の孫は,第15代応神天皇の妃となり,そのうちの一人は皇后としてのちの第16代仁徳天皇を産む。こうして尾張氏は,4世紀終わりから5世紀の初めには,ヤマト王権で大きな力を持つようになる。
5世紀の終わりには,16世孫の尾張連草香の娘の目子郎女が第26代継体天皇妃となり,のちの第27代安閑天皇,第28代宣化天皇を産むなど,皇位継承にも影響力を持つようになる。